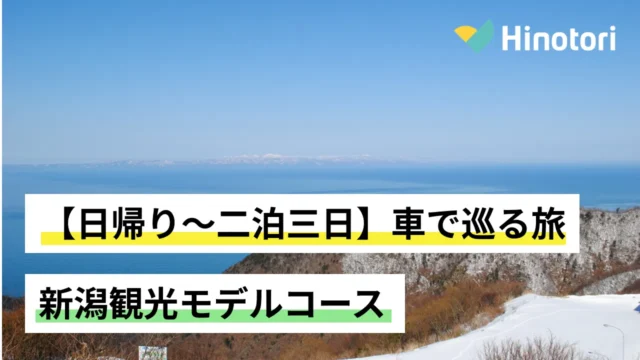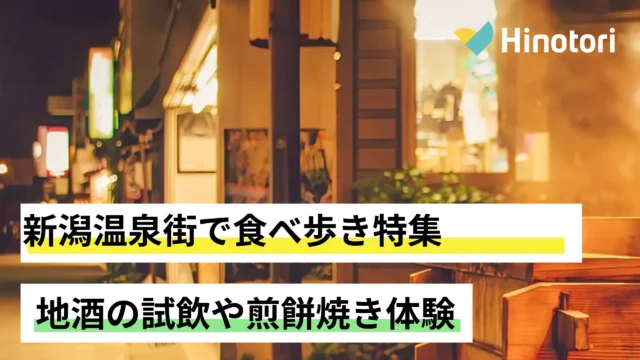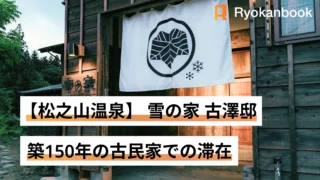今回紹介するのは新潟県十日町市・松之山温泉の「酒の宿 玉城屋」。ここは日本酒とワインが1000種以上そろい、地域の食材で組み立てた料理をペアリングで楽しめます。松之山温泉は日本三大薬湯のひとつとしても知られています。
玉城屋の料理は『ミシュランガイド新潟2020特別版』でフランス料理の一つ星を受賞。宿のご主人 山岸裕一さんはソムリエで、利き酒師の上位資格「酒匠」も持つ方です。
訪れたのは7月下旬の真夏。チェックイン、温泉、ディナーの日本酒ペアリング、翌朝の時間まで、一泊二日の流れを等身大でまとめます。
こんにちは。私は現在台湾に住む大学生です。日本各地をめぐる旅を通じて、人と土地、そしてその土地に根ざす暮らしの姿にふれることを楽しみにしています。
“酒に特化した小さな宿”の強み


玉城屋は、その名のとおりお酒に振り切った宿です。日本酒とワインは1000種類以上、ここでしか体験できないお酒がたくさんあります。小規模だからこそ、食事のペアリングをその日の食材やお客様の表情にあわせて調整してくれます。コースの途中で「今日は酸が立つ方が合いそうですね」など、現場で微調整が入るのもここならではです。接客は押しつけがなく丁寧で、説明は具体的。ソムリエであり「酒匠」の資格を持つオーナーの知識がベースにあるため、提案に迷いがなく安心して任せられます。ちなみに「酒匠」認定者は570名のみで、難易度の高さを物語っています。

過ごし方はとにかく自由で静か。館内の風呂付き客室に泊まれば、ほぼ他のお客さんと接することはありません。チェックイン後は温泉に入って一息、夕食はダイニングでペアリングを楽しみ、部屋に戻ってからも静かに余韻を味わえます。
料理は“新潟で完結”が基本です。魚、野菜、発酵、米——できる限り県内の食材で組み立て、皿の上で新潟をそのまま体験させてくれます。宿で提供されるお米もオーナー・山岸さんが食べ比べて選んだ銘柄。背景を知ると、同じ一口でも味の説得力が変わるのを実感します。
こんな人に向いています。
- 記念日・誕生日など、一泊の滞在で、最高級の料理とお酒でお祝いしたい
- 日本酒やワインのペアリングを本気で楽しみたい
- 静かに過ごしたい(小規模・風呂付き客室で完結できる)

そして、玉城屋の“今”を作ったのが四代目・山岸裕一さんです。
玉城屋はもともと家族経営の伝統旅館でしたが、四代目の山岸裕一さんは東京で和食の修行をしたのち、「戻るなら日本酒に賭ける」と決めて、“酒の宿”への転換に踏み切りました。最初は「特化しすぎでは」「お客様が減るのでは」という反対もあったそうですが、自分が本当においしいと思うものだけを出すという方針を崩さず、ソムリエ/酒匠としての知識と現場感で形にしてきました。結果、今の「料理×日本酒(ワイン)のペアリング」を軸にしたスタイルが根づき、“酒の宿”として支持を集めています。
要は、玉城屋は好きなことに正面から振り切った宿です。ラインナップの豊富さに加え、ひとり一人に合わせた接客で、ゲストの満足度を高めている。ここが“酒の宿”としての本当の価値だと感じました。
チェックイン|ジンの泡とメロンタルトで始まる


フロントで一息つくと、まずジンソーダのウェルカムドリンクが出てきます。最初の一杯から「ここは酒の宿だな」とはっきり伝わります。冷えた炭酸が喉に気持ちよく、移動の疲れが抜けていきます。

そしてお部屋に入ってすぐに出たのはメロンのタルト。小ぶりで見た目が可愛いタイプで、正直、写真を撮りたくなります。サクっとした土台に、みずみずしいメロンの甘さ。重たくないので、甘いものが好きな人にはちょうどいい一皿です。女性はもちろん、スイーツ好きなら素直にうれしいはず。チェックイン直後から“お酒×スイーツ”の世界観に入れるので、この先のペアリングへの期待も自然と上がりました。
【玉城屋 露天風呂付き客室】檜の間で味わう、五感がほどける静け

露天風呂付きの「檜」という部屋に泊まりました。いちばん印象に残ったのは床です。木を彫ったような凹凸があって、素足で歩くと気持ちいい。部屋全体が木の温もりに包まれていて、すぐ落ち着けます。ベッドはシモンズ製で、体の力が抜ける感じ。正直、ここまでぐっすり眠れたのは久しぶりでした。小規模な宿ということもあり、“楽しむ”より“休む”に向いていると感じます。

朝は早起きして檜の露天風呂へ。源泉掛け流しなので共用のお風呂より熱めで、自分で水を足して温度調整します。これは少し難しかったですが、周りは自然に囲まれていて、湯気越しの緑が気持ちいい。一日の始まりにちょうどいい静けさでした。設備や導線は分かりやすく、海外の方でも不自由なく過ごせる印象です。
お湯については、松之山温泉が日本三大薬湯のひとつと言われるだけあり、入ったあとはリラックスというより“回復”に近い感覚が残ります。塩分が効いているのか、体が少し浮くような感覚があり、上がると肌がつるつるになりました。

アメニティはサステナブル志向で、竹製の歯ブラシが用意されています。約1か月使えるとのことで実用的。こういうさりげない配慮も含めて、本当にリラックスできる環境が整っていると感じました。
——総じて、「檜」は“観光で動き回る”より“よく休む”ために選びたい部屋です。床の心地よさ、木のぬくもり、ベッドの寝やすさ、そして湯の力。どれも素直に“効く”要素ばかりでした。
姉妹館「睡夢」|バー&ダイニングと貸切サウナ


姉妹館の「睡夢(すいむ)」には、貸切のサウナと小さなバーがあります。私たちは夕食前にサウナを利用しました(事前に相談可 宿泊者は希望すればチェックイン前の時間帯にも利用可能)。室内は余計な演出がなく、しっかり熱が入ります。水風呂はわさび沢の水でやわらかいあたり。休憩スペースも静かで、呼吸が整いました。

上がってから食べたソフトクリームがよく染みて、体温と気持ちがちょうどいいところに戻ります。
そのあと玉城屋に戻って身支度をしてディナーへ。整った状態で新潟食材のコースと日本酒のペアリングに入れるので、味がすっと入ってきます。

夜は余力があれば、再び「睡夢」のバーで一杯。無理のない流れで一日がつながる感じがよかったです。
【夕食】ローカルガストロノミーを堪能|地元食材と日本酒ペアリング

いよいよ夕食の時間です。選んだのは料理長・栗山昭氏による創作フレンチと、オーナー・山岸裕一さんが手がけるプレミアム日本酒ペアリングのコース。この“美酒美食の競演”こそ、玉城屋でしか体験できない贅沢なひとときです。
栗山シェフは東京出身ながら、新潟の食材に惚れ込み、地元の農家を自ら訪ね歩いておられます。時には山菜を自ら採取することもあるそうです。その情熱は皿の上に表れ、伝統とモダンが融合したような独創的な料理が、次々と登場しました。
そして、これらの料理に寄り添うのが、山岸さんが選び抜いた日本酒の数々。彼は、ソムリエ資格に加え、日本酒のプロ中のプロとされる酒匠(さかしょう/利き酒師の上位資格)の資格を持っておられます。その知識と経験は新潟県内でも随一で、県内外の酒蔵やワイナリーを実際に訪ね歩き、自分の舌で選んだお酒だけを提供しています。中には、彼が蔵元と共同開発したオリジナルのプライベートブランド酒もありました。
今回堪能したコース料理を、一つひとつご紹介していきます。
アミューズ三種 × プライベートブランド KAMOSU MORI(ほうじ茶+ハイビスカスを使ったスパークリング風)


美雪鱒やレバーパテ、妻有ポークの生ハムなど小品の盛り合わせに合わせて、プライベートブランド酒である「KAMOSU MORI」をいただきました。華やかかつ爽やかな口当たりが、コースの始まりに軽やかさを添えてくれました。
とうもろこしのスープ × SAKE HUNDRED 弍光

地元産の牛乳ととうもろこしだけで作られたやさしい甘味のスープに、アロマティックな日本酒「弍光」が調和していました。多くの日本酒は米・麹・水を3回に分けて投入する「三段仕込み」で造られますが、「弐光」は、そこからもう一度仕込みを行う「四段仕込み」×「白麹」という特別な方法で造られており、旨味や酸味を感じる、より上品な味わいを堪能することができます。
真鯛のマリネ(ズッキーニ・リコッタチーズ・トマトコンフィ/紫蘇トマトソース × あべ 十周年記念純米大吟醸 白
昆布締め真鯛と紫蘇が爽やかに調和していました。そこに、新潟県にある「阿部酒造」のドライで優しい酸のある日本酒が見事にマッチ。
大長茄子焼き茄子ムース(茄子ムース・南蛮エビ・甲殻ジュレ) ×松乃井 純米大吟醸

上層には地元産の大長茄子を使ったムースとチップス、中層には山椒の香りを移したオイルで調理した南蛮エビ、下層には甲殻類の旨味が詰まったジュレが敷かれており、食べ進めるごとに異なる風味が楽しめます。山椒の爽やかさが全体を引き締め、まさに体験型の一皿でした。ペアリングの日本酒は、100年以上の歴史を持つ十日町の酒蔵・松乃井酒造場のもの。フルーティすぎずすっきりとした口当たりで、料理の味を引き立てます。
サザエのコンフィ/肝ソース・きゅうり・おかひじき揚げ × SAKE マルゲリータ(トマト&バジル風味)

磯の旨味とほろ苦さがしっかりと感じられる一皿に寄り添うのは、トマト&バジル風味の日本酒「酒マルゲリータ」。日本酒の醸造過程で実際にトマトとバジルを加えているそうで、まるでマルゲリータピザを味わっているかのような風味です。それでいてサザエとも相性が良く、一種のエンターテインメントを思わせる組み合わせでした。
甘鯛× Maison Aoi Untitled 01,2025
米茄子の揚げ煮と夕顔ソースが上品な旨味と彩りを引き立て、日本酒「Maison Aoi Untitled 01,2025」の爽やかさが味をまとめてくれました。こちらの日本酒は、新潟県長岡市の酒造・葵酒造の銘柄。葵酒蔵は、2024年に江戸時代から続いた高橋酒造を新しいチームメンバーが引き継いでできた酒蔵で、新潟から日本全国、そして世界へ目を向けて日本酒作りに取り組んでおられるそうです。
鹿ロースト(ポワヴラードソース)×真野鶴 佐渡金山貯蔵 熟成純米酒 2013


次に出されたのは、鹿肉のロースト。熟成された日本酒とともに味わうことで、鹿肉の旨味を一層引き立て、食事の余韻が深く豊かに広がっていきました。女性猟師が仕留めた鹿肉を使用しているという点にも心を惹かれました。
「真野鶴」は佐渡島の旧・真野町にある酒蔵で造られた日本酒です。真野鶴は全国新酒鑑評会(日本)、International Wine Challenge(イギリス)、Kura Master(フランス)、Milano Sake Challenge(イタリア)などで数々の金メダルを受賞しています。
青胡桃と桃の和デセール(寒天・黒豆・ミント) × 東方美人茶(ノンアルコール)
珍しい青胡桃や地元産の桃に、寒天や黒豆を添えた一品です。和の味わいにミントのシロップを合わせ、爽やかさと滋味が共存する繊細な和デセールでした。こちらにはノンアルコールの「東方美人茶」を合わせていただきました。
メロンソーダ風デザート(三層:炭酸メロンムース・バニラアイス・レモングラスゼリー) × Fomalhaut
炭酸メロンソーダにバニラアイスとレモングラスゼリーを合わせた、爽やかで遊び心のあるデザートと、阿部酒造の貴醸酒タイプの日本酒「FOMALHAUT」をペアリング。デザートワインのような甘味と酸味が、爽やかなデザートと相性がとてもよかったです。
ハーブティーと4種のデザート
デザートの締めくくりには、香り豊かなハーブティーとともに、趣の異なる4種類の小さなデザートが供されました。
日本酒ペアリングコースにはスタンダードとプレミアム、お酒が苦手な方はノンアルドリンクでのペアリングも可能です。
台湾でも近年、日本酒の人気が高まりつつあり、酒蔵見学や地酒の試飲を目当てに旅行する友人も多くなっています。とはいえ、ここでの体験は“ただ飲む”という域を超え、日本酒の奥深さと料理の妙、そして空間そのものが織りなす、五感を満たす総合的な「体験」でした。みなさんもきっと、食材・ペアリング・空間の三位一体に驚かされることでしょう。
朝のごちそう|新潟魚沼産コシヒカリ・野菜を堪能できる朝食

ダイニングに着くと、まず大きなお皿に山菜や旬の野菜が少しずつ。どれも主張が強すぎず、素材の味がそのまま伝わってきます。季節によっては料理長が山に入って採ってくる山菜も出ると聞き、思わず「そりゃおいしいはずだ」とうなずきました。
私は朝から濃い味は得意ではないのですが、ここはやさしい塩加減で箸が止まりません。窓の外に山の緑。深呼吸してから一口食べるだけで、体が起きていく感じがしました。
そして魚沼産コシヒカリ。炊きたての湯気が上がって、まず香りでやられます。噛むと甘みがちゃんと出て、思わずおかわり。台湾の朝ごはんも好きですが、新潟の大地をそのまま味わうように、そこで育った米や野菜を食べるという発想はここならではだと素直に感じました。小鉢や副菜も多すぎず、ちょうどいい量。体に負担がかからない朝食で、旅の後半に向けてしっかりエネルギーが戻りました。
まとめ|玉城屋ご主人・山岸さんの想い
ご主人の山岸裕一さんは、東京で和食を学んだあと地元に戻り、「酒の宿」へ舵を切った四代目。日本酒の蔵やレストランを自分の足で回り、納得したものだけを集め、オリジナルの日本酒づくりにも踏み込む——話を聞くほど、“好きに正面から向き合う人”だと分かります。
もう一つ印象に残ったのは、非日常の中にある安心感。小さな宿だからこそ、声のかけ方やタイミングが丁寧で、こちらのペースを見てくれます。ペアリングも“押しつけ”ではなく、その日の体調や表情に合わせて微調整。結果、こちらも肩の力が抜けて、食と酒をまっすぐ楽しめる時間になりました。実は私も普段お酒はあまり飲まないので、ペアリングは正直不安でした。ですが、コースの合間に私の様子を見てノンアルコールドリンクを提案・提供していただき、山岸さんやスタッフの心遣いがじんわり伝わってきました。
玉城屋で過ごした一泊は、単なる宿泊ではなく、五感で土地を味わい、ほどよく自分が緩む体験でした。力のある湯、やさしい料理、心が動くお酒、そして静けさ。ぜひまた訪れたいと素直に思いました。
台湾と雪国・新潟は気候も文化も違いますが、だからこそここを訪れる意味があります。アクセスもしやすく(台北—新潟の直行便もあります)、日本酒や温泉、ローカルガストロノミーに興味がある方には、松之山温泉の「酒の宿 玉城屋」を強くおすすめします。
基本情報
スポット名:酒の宿 玉城屋
住所:〒942-1432 新潟県十日町市松之山湯本13
https://maps.app.goo.gl/U27ZadcUJda9fsEMA
電話番号:025-596-2057
アクセス:
・車:関越道六日町インターより60分
・列車:ほくほく線「まつだい駅」よりバスで20分
・飛行機:台北空港から新潟空港まで約3時間10分、新潟空港から車で約2時間15分
「酒の宿 玉城屋」の予約はこちら:https://www.ryokan-book.com/jp/area/tokamachi/ryokan/tamakiya/
日本三大峡谷のひとつ、清津峡へ

翌日の朝、玉城屋をあとにして、 清津峡へと出発しました。
新潟県・十日町市にある 清津峡(きよつきょう) は、黒部峡谷・大杉谷と並ぶ 日本三大峡谷 のひとつとして知られています。
かつては登山道からその絶景を楽しむ場所でしたが、現在では、まったく新しいかたちで世界中の人々を魅了する名所となっています。
今回は、清津峡の「歩いて体感するアート」と、そこに息づく自然・歴史の魅力を堪能してきました。
【清津峡とは】自然が創り出した巨大な柱状節理

清津峡は、柱状節理(ちゅうじょうせつり)と呼ばれる六角柱の岩が連なる独特の地形が特徴で、その景観は1941年に国の名勝・天然記念物に指定されました。
約1500万年前、海底火山の噴火によってできた地層にマグマが流れ込み、冷えて固まることで生まれたこの柱状の岩たち。
長い年月をかけて清津川がその岩を削り、現在のようなV字の谷が形づくられました。
まさに、自然が生み出した巨大な彫刻とも言えるこの地形は、地質学的にも学術的にも非常に貴重なものです。
【トンネルへ】Tunnel of Light を歩く

少しだけ清津峡の歴史をたどると――1996年、安全に峡谷美を楽しめるようにと「清津峡渓谷トンネル」が開通。
しかし観光客の減少により、再び注目を集めるきっかけとして2018年に大きなリニューアルが施されました。
建築を手がけたのは、中国出身の建築家マ・ヤンソン率いるMADアーキテクツ。
自然と建築、アートを融合させたこのトンネルは、「Tunnel of Light(光のトンネル)」というアート作品として生まれ変わります。

トンネル内は、さまざまな色の光に照らされ、時間や角度によって表情を変えます。
その中でも印象的だったのは、風とも水音とも言えないそのサウンド。まるでこのトンネルそのものが呼吸をしているようです。
【見晴所の数々】自然と一体化するアート体験
トンネル内には全部で3か所の見晴所があります。
それぞれが個性的な空間アートとして設計されており、まさに「歩くアート鑑賞」と言える体験ができます。
第二見晴所「Flow」

清津川の流れが壁や床のストライプに反映されるようにデザインされ、空間全体が水の流動性を表現。
実はこの銀色の物体の中はトイレ。内側からだけ外が見えるマジックミラーで、トイレすらも作品の一部。なんとも不思議な感覚になりました。
第三見晴所「しずく」

湾曲した壁に無数のしずく型の鏡が散りばめられ、自分自身の姿もアートの一部に。
夕暮れ時には背後から灯る赤いライトが、空間をじわじわと染め上げます。
それぞれの見晴所では、峡谷の岩肌がすぐ目の前に広がり、人工物であるトンネルと大自然が不思議なバランスで共存しています。
【パノラマステーション】水鏡に映るもう一つの峡谷

トンネルの終点にあるのが、パノラマステーション「ライトケーブ(光の洞窟)」です。
この空間は、私にとって一番印象的でした。
足元には水が張られ、上からの光や景色を反転して映す「水鏡」が広がっています。
半鏡面のステンレスで囲まれた空間に、峡谷の緑や岩肌が反射し、本物の景色なのか、映像なのか、一瞬わからなくなるほど幻想的。
そして、その水の中に足を入れると、ひんやりとした冷たさが足元から身体に伝わり、まるで自分がこの峡谷の一部になったような気持ちになりました。
パノラマステーションの余韻と足湯での静かなひととき

パノラマステーションでの幻想的な景色を思う存分堪能した後は、清津峡の入口にあるエントランス施設へ戻る途中、ちょっと立ち止まるのにぴったりのスポットがあります。
それが、清津峡温泉郷・エントランス施設 ペリスコープ(清津峡渓谷トンネル入口の2階)にある足湯です。

トンネルの冷たい空気から戻ってきた体に、この温かさがじんわり染み渡るようで、旅の疲れや感動が湯気とともにほぐれていくようでした。
泉質は単純硫黄温泉で、温度は約41度。神経痛・筋肉痛・関節痛などに効能があるとされ、この自然の中での足湯タイムは、まさに癒しそのものです。もし訪れる季節が冬でなければ、ぜひこの足湯で旅の締めくくりに心と体をゆるめてほしいと思います。
【まとめ】この土地が問いかけるもの

清津峡の「Tunnel of Light」は、単なる観光施設ではなく、自然と人間が共鳴するための“通路”のような場所です。
私自身、トンネルを歩きながら、音に耳を澄まし、光の揺らぎを感じ、足元の水の冷たさに触れ、気づけば何度も深呼吸をしていました。
それは、普段の生活で見失いがちな「自然との距離感」を取り戻すような時間だったのかもしれません。
清津峡は、ただ美しいだけではなく、自然の力強さと脆さ、人間との関係性を静かに問いかけてくれる素敵な場所です。写真を撮りたい方は、人の少ない朝いちがおすすめ。
もし、日常の喧騒から少し離れて、自分の感覚を取り戻したいと思ったときは、ぜひこのトンネルを訪れてはいかがでしょうか。
基本情報
名称:清津峡(きよつきょう)
住所:〒949-8433 新潟県十日町市小出癸2119-2
電話番号:025-763-4800(清津峡渓谷トンネル管理事務所)
交通アクセス:
- 車:関越自動車道「塩沢・石打IC」より国道353号線へ車で約25分
- 電車、バス:清津峡入口バス停まで(下車後徒歩約30分)
- JR東日本「越後湯沢駅」より森宮野原行き急行バスで約25分
- JR飯山線「越後田沢駅」よりバスで約20分
- 飛行機:台北(桃園国際空港)から新潟空港まで約3時間10分。新潟空港から車で約2時間30分。